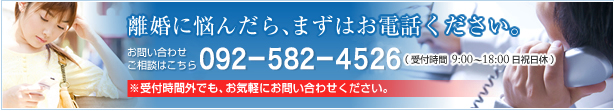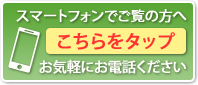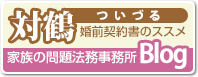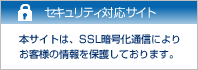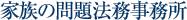よくある質問
離婚についての質問
夫に離婚を切り出すことができないのですが?
夫婦間の話し合いで協議がまとまらない場合は家庭裁判所を利用した調停の申し立てなどもあります。
しかし、いきなり調停というよりはまずじっくりと話を進めるべきです。
離婚を切り出すにはかなりのエネルギーを必要とします。
相手方にいつ、どのように伝えればよいのか解らないとおっしゃる方は大勢います。
そういうことでお悩みの方は手紙であなたの考えを伝えてもいいのではないでしょうか。
お手紙が苦手な方は、当サイトのお手紙代書サービスをごらんください。
しかし、いきなり調停というよりはまずじっくりと話を進めるべきです。
離婚を切り出すにはかなりのエネルギーを必要とします。
相手方にいつ、どのように伝えればよいのか解らないとおっしゃる方は大勢います。
そういうことでお悩みの方は手紙であなたの考えを伝えてもいいのではないでしょうか。
お手紙が苦手な方は、当サイトのお手紙代書サービスをごらんください。
必ずということはありませんが、お子さんがまだ幼ければ母親のほうが断然有利です。
が、離婚後の経済状態があまりにも不透明な場合は、そうとも限りません。
まずは資格取得や技能を身につけることも必要です。
ご実家に戻るなども考えてはいかがでしょう。
が、離婚後の経済状態があまりにも不透明な場合は、そうとも限りません。
まずは資格取得や技能を身につけることも必要です。
ご実家に戻るなども考えてはいかがでしょう。
慰謝料は、相手のせいで離婚しなければならなくなったことによる精神的苦痛についての損害賠償です。
どのくらい請求できるのかは、ケースにより大きく異なりますので、専門家に相談して下さい。
どのくらい請求できるのかは、ケースにより大きく異なりますので、専門家に相談して下さい。
お互いの経済力にもよりますが、一般的には、子供1人あたり毎月3万円から5万円程度です。
養育費を支払う側の生活が困窮するようではもともこもないので、お互いよく話し合って決めてください。
あくまでも相場は目安です。
最近は年齢により段階的に金額を変えていく方法も多くもちいられます。
養育費を支払う側の生活が困窮するようではもともこもないので、お互いよく話し合って決めてください。
あくまでも相場は目安です。
最近は年齢により段階的に金額を変えていく方法も多くもちいられます。
子供の戸籍と姓は、離婚前と同じです。両親の離婚による影響を受けません。
例えば、父親が戸籍の筆頭者であった場合、母親が親権者で同居をしていても、子供の戸籍と姓は父親と同じになります。
母親が結婚前の籍に戻った場合は、自分が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍を作り、子供の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立書を提出します。
家庭裁判所に子供の姓の変更が認められれば、許可審判書が交付されますので、市区町村役場に入籍届けを添えて提出します。
子供が15歳以上の場合は、本人の意思により戸籍と姓の変更の許可を申し立てることができます。
例えば、父親が戸籍の筆頭者であった場合、母親が親権者で同居をしていても、子供の戸籍と姓は父親と同じになります。
母親が結婚前の籍に戻った場合は、自分が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍を作り、子供の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立書を提出します。
家庭裁判所に子供の姓の変更が認められれば、許可審判書が交付されますので、市区町村役場に入籍届けを添えて提出します。
子供が15歳以上の場合は、本人の意思により戸籍と姓の変更の許可を申し立てることができます。
内縁関係とは、結婚の意思が双方にあり共同生活を営んでいるが、婚姻届を出していない男女の関係をいい、婚姻に準ずる関係とされています。
内縁の夫婦には、法律上の夫婦と同様に、同居義務、貞操義務、協力義務、扶助義務婚姻費用分担義務があります。
内縁関係にある二人の一方が、相手の合意なしに内縁関係を解消しようとした場合(内縁関係の不当破棄)、内縁関係は婚姻に準ずる関係にあるため、もう一方は、法的保護を受けることができます。
したがって、相手が一方的に内縁関係の解消を申し出た場合には、慰謝料を、夫婦共有の財産がある場合には、財産分与を請求できます。
また、話し合いで解決できない場合は、法律上の夫婦の場合と同様に、調停を申し立てることができます。
内縁の夫婦には、法律上の夫婦と同様に、同居義務、貞操義務、協力義務、扶助義務婚姻費用分担義務があります。
内縁関係にある二人の一方が、相手の合意なしに内縁関係を解消しようとした場合(内縁関係の不当破棄)、内縁関係は婚姻に準ずる関係にあるため、もう一方は、法的保護を受けることができます。
したがって、相手が一方的に内縁関係の解消を申し出た場合には、慰謝料を、夫婦共有の財産がある場合には、財産分与を請求できます。
また、話し合いで解決できない場合は、法律上の夫婦の場合と同様に、調停を申し立てることができます。
婚姻費用や慰謝料、財産分与、養育費といったお金の約束は、約束をしたからといって安心はできません。
約束を守らない人などは大勢いるからです。
離婚後、初めは毎月養育費の支払いを行っていたが、途中で元夫が再婚し支払いをやめてしまうことなどよくあります。
支払いの催促をして、すぐに支払ってもらえれば良いのですが、相手に支払う意思がまったくないこともあります。
このようなことを回避するためにも、法的に有効な手続きを事前に行い、支払いを確実に行わせるようにしておきましょう。
より確実にするため公正証書での離婚協議書の作成をお勧めします。
約束を守らない人などは大勢いるからです。
離婚後、初めは毎月養育費の支払いを行っていたが、途中で元夫が再婚し支払いをやめてしまうことなどよくあります。
支払いの催促をして、すぐに支払ってもらえれば良いのですが、相手に支払う意思がまったくないこともあります。
このようなことを回避するためにも、法的に有効な手続きを事前に行い、支払いを確実に行わせるようにしておきましょう。
より確実にするため公正証書での離婚協議書の作成をお勧めします。
離婚協議書の作成をお願いしたいのですが?
はい。全国どこからの依頼でも対応可能です。料金等はこちらをごらんください。
離婚後の住居が不安なのですが?
離婚が決まっていれば、籍が入っていても、母子の名前で市営住宅等に応募できる場合がありますので居住地の役所に問い合わせてみてください。
児童扶養手当とは?
18歳未満の子供がいる場合で、一定以下の収入であれば、児童扶養手当が受給できます。
実家で暮らす場合でも、世帯全体の収入が一定基準以下であれば、受給は出来ます。
実家で暮らす場合でも、世帯全体の収入が一定基準以下であれば、受給は出来ます。
専業主婦ですが、年金分割とはどんな制度ですか?
御主人がサラリーマンや公務員の場合あなたは3号被保険者に当たります。
平成20年4月より分割する場合は2分の1という法定分割制度が始まりましたが、それ以前の分はお互いの協議で解決します。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所に決めてもらうことになります。
分割が決まれば、公正証書か公証人の私署証書が必要となります。
平成20年4月より分割する場合は2分の1という法定分割制度が始まりましたが、それ以前の分はお互いの協議で解決します。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所に決めてもらうことになります。
分割が決まれば、公正証書か公証人の私署証書が必要となります。